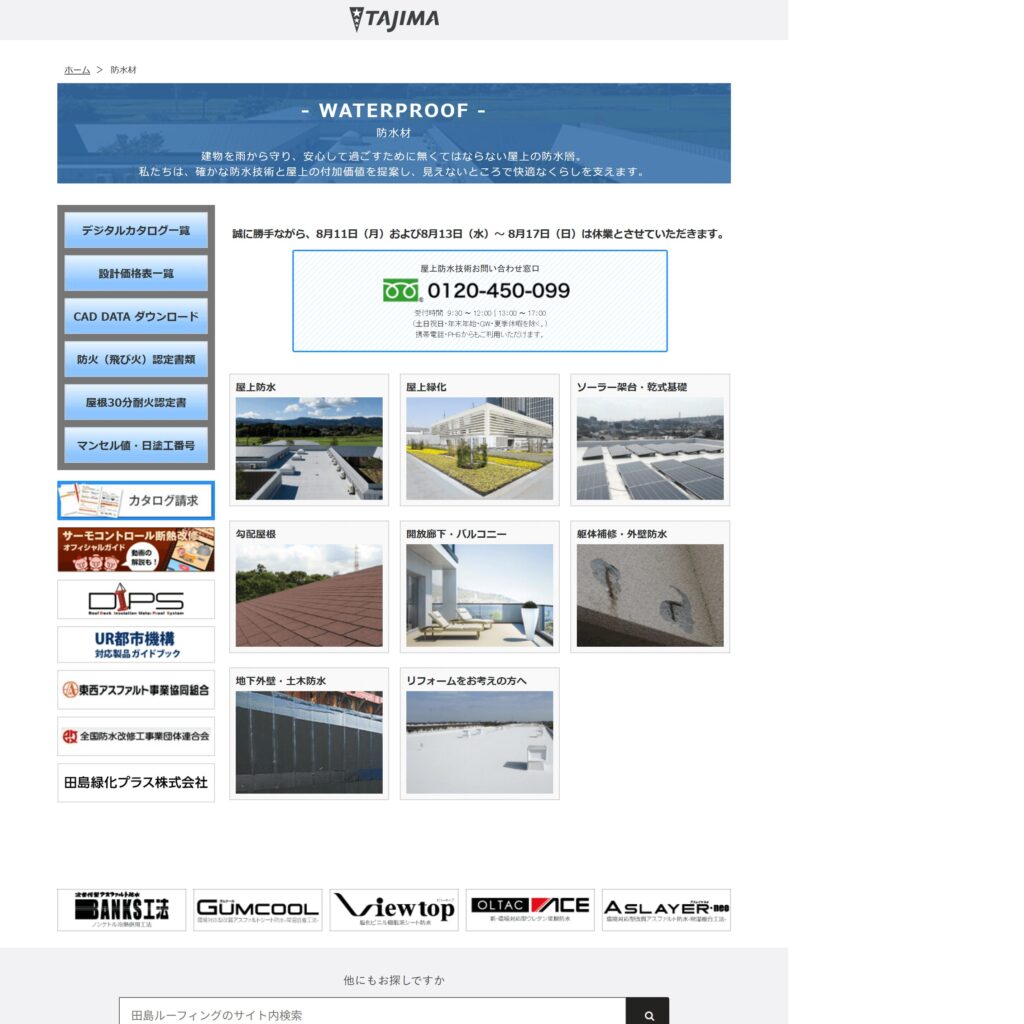ウレタン防水工事を検討中の人にとって、天候は重要な要素です。とくに雨の日の施工については、品質への影響を心配される人も多いでしょう。実際、雨天時のウレタン防水工事には大きなリスクが伴います。しかし、すべての作業が不可能というわけではありません。本記事では、雨の日のウレタン防水工事について詳しく解説します。
雨の日のウレタン防水は基本NG
ウレタン防水工事において、雨天時の施工は原則として避けるべきです。その最大の理由は、ウレタン防水材の硬化プロセスに水分が悪影響を及ぼすことにあります。ウレタン防水材は、主剤と硬化剤を混合することで化学反応を起こし、防水層を形成します。この化学反応の過程で水分が混入すると、正常な硬化が妨げられ、防水層の品質が著しく低下してしまうのです。また、雨水が直接防水材に触れると、表面が白濁したり、ムラができたりすることもあるでしょう。
さらに深刻なケースでは、防水層が剥離してしまい、まったく防水機能を果たさなくなることさえあります。日本ウレタン建材工業会の施工指針でも、降雨時および降雨が予想される場合の施工は避けるよう明記されています。
仮に小雨程度であっても、湿度が85%を超える環境では施工を控えることが推奨されているのです。これは、高湿度環境下では空気中の水分がウレタン防水材の表面に結露として付着し、硬化不良の原因となるためです。
プロの防水工事業者は、天気予報を綿密にチェックし、施工後24時間以内に降雨が予想される場合は工事を延期します。
ただし、近年では速乾性に優れた硬化が早いウレタン防水材も開発されており、施工後3~6時間程度で雨に耐えられる製品も登場しています。このような製品を選択することで、天候リスクをある程度軽減することが可能です。
調査・洗浄作業なら行っても問題ナシ
雨天時でもウレタン防水工事に関連するすべての作業が不可能というわけではありません。防水工事の前段階である調査作業や下地処理の一部については、雨の日でも実施可能な場合があります。現地調査や劣化診断については、雨天時のほうが有益な情報を得られることもあるでしょう。雨が降っている状態で建物を観察することで、実際の雨水の流れや水たまりができやすい箇所、雨漏りの発生箇所などを正確に把握できます。これらの情報は、防水工事の計画を立てる上で非常に重要な要素となります。
また、高圧洗浄による下地清掃作業も、雨天時に実施することが可能です。もともと大量の水を使用する作業であるため、雨が降っていても作業への影響は限定的といえるでしょう。ただし、洗浄後は下地を完全に乾燥させる必要があるため、その後の工程スケジュールには注意が必要です。
さらに、既存防水層の撤去作業についても、材料の種類によっては雨天時でも実施できます。たとえば、シート防水の撤去やアスファルト防水の除去作業などは、雨の影響を受けにくい作業といえるでしょう。
一方で注意すべき点として、下地補修作業は雨天時には適さないことが挙げられます。モルタルやコンクリートを使用した補修作業は、雨水によって材料が流れ出したり、強度不足を引き起こしたりする恐れがあります。
同様に、プライマー塗布作業も雨天時には実施できません。プライマーは下地とウレタン防水材を密着させる重要な役割を担っており、水分が混入すると接着力が大幅に低下してしまうためです。
このように、雨天時でも可能な作業と不可能な作業を明確に区別し、天候に応じて柔軟に工程を組み替えることが、効率的な防水工事の実現につながります。経験豊富な業者であれば、天候を考慮した最適な工程管理を行い、品質を確保しながら工期の遅延を最小限に抑えることができるでしょう。
雨漏りを見つけた際の応急処置
突然の雨漏りを発見した場合、最初に行うべきなのは、雨漏り箇所の特定と被害の拡大防止です。天井から水が垂れている場合は、バケツやタライを設置して床や家財への被害を防ぎます。次に、可能であれば雨漏りの原因箇所を確認します。屋根や外壁のひび割れ、シーリング材の劣化、排水口の詰まりなどが主な原因として考えられます。
応急的な補修方法として、防水テープやコーキング材を使用する方法も有力です。小さなひび割れや隙間であれば、市販の防水テープを貼ることで一時的に雨水の侵入を防げます。より確実な処置を求める場合は、変成シリコン系のコーキング材を使用するとよいでしょう。
屋根の破損が原因の場合、ブルーシートによる養生が効果的です。破損箇所を覆うようにシートを設置し、土のうや重しでしっかりと固定します。このとき、シートの端部を高くして水が流れやすいように設置することがポイントです。
室内側の対策として、雨漏り箇所周辺の家具や電化製品を移動させ、カビの発生を防ぐために換気を心がけることも大切です。また、雨漏りの状況を写真や動画で記録しておくと、後日業者に修理を依頼する際の重要な資料となります。
これらの応急処置はあくまで一時的な対策であり、根本的な解決には専門業者による本格的な防水工事が必要です。
とくに、硬化が早いウレタン防水材を使用した工事であれば、天候の隙間を見て迅速に施工を完了させることができ、雨漏りの再発リスクを大幅に低減できます。早期の対応が建物の寿命を延ばし、修繕コストの削減にもつながることを認識しておきましょう。