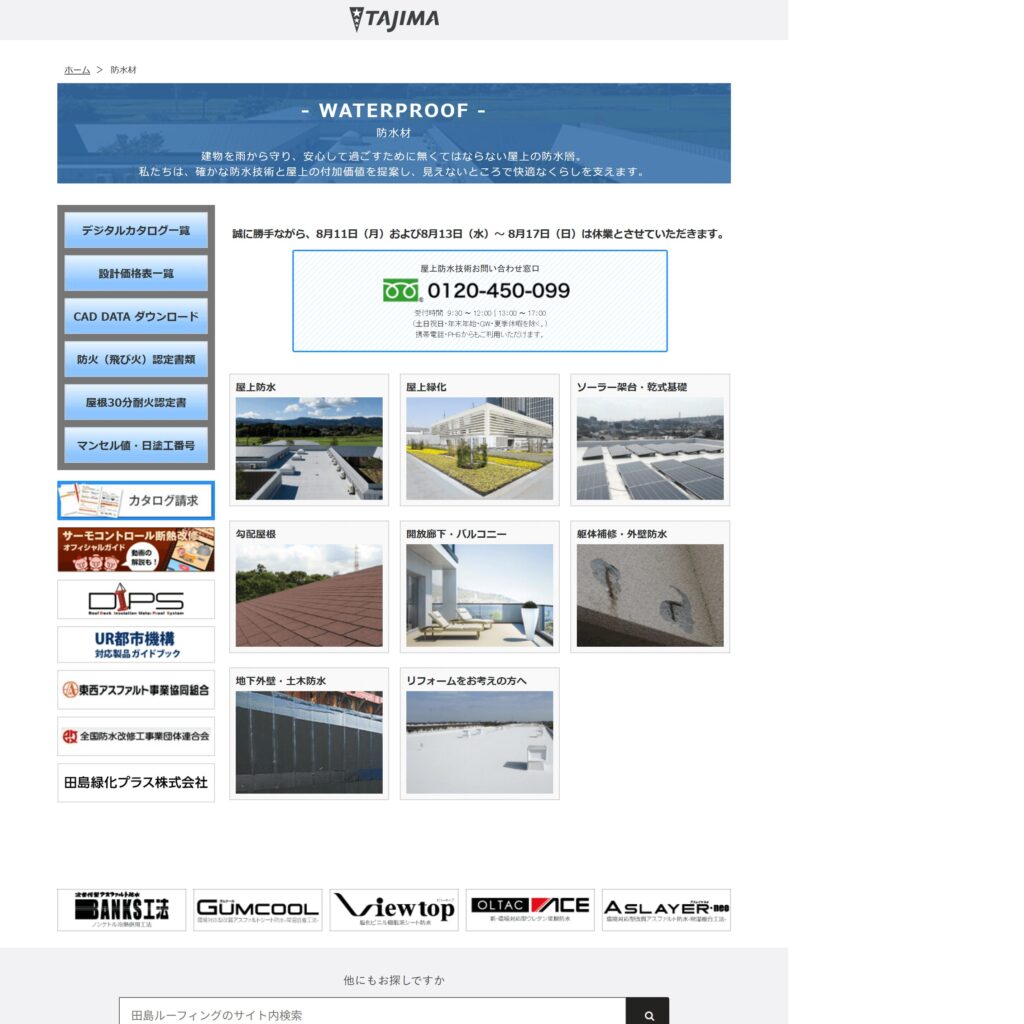ウレタン防水は柔軟性に優れ、さまざまな建物で採用される代表的な防水工法です。しかし、施工をする際には乾燥時間を正しく守らなければ、不具合や思わぬトラブルの原因となることがあります。この記事では、各工程ごとの乾燥時間の目安や注意点、乾燥不良によって起こり得るトラブルなどについて詳しく解説します。
ウレタン防水の硬化・乾燥時間の目安
ウレタン防水工事では各工程ごとに適切な乾燥時間を確保することが仕上がりや耐久性を左右する重要なポイントです。まず、下地と防水層の密着を高めるプライマーは塗布後1〜2時間ほど乾燥させる必要があります。その上に塗るウレタン主剤は、初期硬化までおよそ24時間置きましょう。さらに仕上げのトップコートは、表面が触れてもべたつかない状態になるまで3〜6時間ほど乾かし、施工から24時間ほど経過で軽歩行が可能になります。
ただし、これらはあくまで目安として定められているものであり、下地の状態や環境条件によって変わるため、メーカーの仕様書を確認しながら判断することが何よりも大切です。
塗膜を厚く塗りすぎると表面だけが乾いてしまい内部が十分に硬化しない場合があるため、複数回に分けて薄く塗り重ねてしっかりと乾燥させることが望ましいでしょう。
乾燥不足のまま次の工程に進んでしまうと膨れや気泡などのトラブルが起こりやすくなってしまうだけでなく、補修の手間や再度施工を行うために時間と労力がかかってしまいます。施工環境に配慮し、焦らず慎重に進めることが高品質と長期的な耐久性を保つカギといえるでしょう。
ウレタン防水の硬化・乾燥に影響する要素
ウレタン防水の乾燥にかかる時間は一定ではなく施工をする際の場所や環境、塗り方や下地の状態などの施工条件によって大きく変動します。乾燥に影響する主な要素と注意点は次の通りです。施工環境
乾燥時間に影響しやすいといわれているのが気温と湿度です。気温が高ければ乾燥は早く進み、低すぎると硬化が遅れ、とくに5℃以下では施工不良のリスクが高まるため作業は避ける必要があります。湿度が高いと表面の白化やベタつきが残ることもあるため注意が必要です。15〜25℃程度の環境が理想的で、梅雨や冬場など気象条件を確認したうえで無理な作業を控え、状況に応じて乾燥時間を長めに取ることがトラブル防止につながります。
塗膜の厚み
ウレタン防水は正しい厚みで施工することで本来の性能を発揮しますが、塗膜が厚くなればなるほど乾燥に時間がかかります。1回あたりの塗布量の上限が決められているケースがほとんどで、厚く塗れば塗るほど良いと思ってたくさん重ねて塗ってしまうと表面だけが硬化してしまいます。これは、内部が十分に固まらないベタつきの原因となりやすいです。表面のみの硬化は内部の膨れや2層目施工時の層間剥離リスクを高めるため、均一な厚さを保ちつつ規定量を守ることが大切です。
換気環境や下地の状態
ウレタン防水の乾燥は、施工する場所の環境や下地の状態や通気性にも大きく左右されます。コンクリートなどに水分が残っていると、塗膜内部で蒸気が発生して膨れや気泡の原因となります。通気性が悪い場合も乾燥が遅くなり、仕上がりに影響を及ぼすことがあります。そのため、施工前には下地の含水率を確認し、必要に応じて適切な対策を行うことが重要です。
ウレタン防水の硬化・乾燥時間を適切に守らないとどうなる?
ウレタン防水施工において乾燥時間を守らないと、塗膜の硬化不良や表面のベタつき、膨れ、気泡、剥がれなどの不具合が発生する可能性があります。表面が乾いて見えても内部が十分に硬化していない場合、トップコートの密着不良や摩耗の原因となり、防水性能にも影響を及ぼすのです。また、乾燥が不十分な状態で重ね塗りを行ってしまうと、塗膜内に水分や空気が閉じ込められ、膨れや気泡、層間剥離や浮きといったトラブルが起こりやすくなります。これらの不具合は施工直後には分かりにくく、数日~数週間後に表面の浮きや亀裂として現れることがあり、防水性能低下や漏水のリスクにもつながります。
さらに、乾燥不良による問題が発生すると再施工が必要になり、下地処理からやり直す手間やコスト、工期の延長が避けられません。引き渡しや他業者の工程にも影響が及び、信頼をなくしてしまったりクレームなどのトラブルにつながる可能性も否定できません。
一時的に作業を急いでも、後戻り作業が増えることでかえって負担が大きくなるため、各工程での乾燥状態を確認し、養生時間を十分に確保することが施工品質の維持とトラブル防止において非常に重要です。