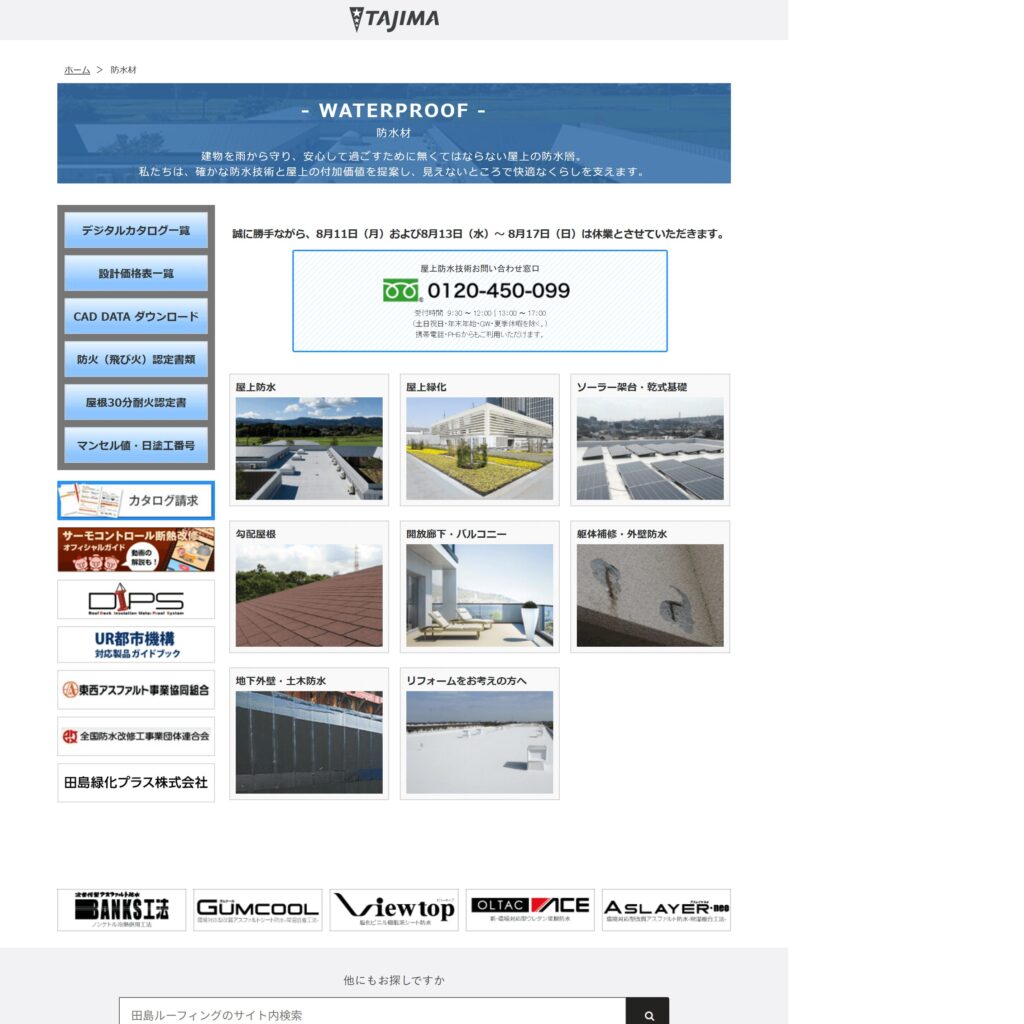防水施工で広く採用されるアスファルト防水ですが、いつかは改修すべき時期がやってきます。ウレタン防水は、軽量で施工性が高く、既存の防水層を撤去せずに施工できる場合もあり、改修工事の選択肢として有効です。この記事では、アスファルト防水からウレタン防水への改修は可能なのか、仕上げ方法や施工条件との関係などを解説します。
アスファルト防水の改修にウレタン防水を用いることは可能
液体材料を塗布することで継ぎ目のない防水層を形成できるウレタン防水は、複雑な形状の下地にも対応しやすく、軽量で建物への負担が少ないのが特徴です。では、アスファルト防水からウレタン防水への改修は可能でしょうか。可能だが相性に注意
アスファルト防水の改修に、ウレタン防水を用いることは可能です。ただし、アスファルト防水の仕上げ方法や劣化状況によって相性が異なるため、事前に十分な確認が必要です。柔軟性に秀でる
ウレタン防水の魅力は、複雑な形状でも施工できる柔軟性にあります。液体を塗布することで継ぎ目のない防水層ができあがり、シート防水では対応しにくい場所にも有効です。耐用年数の目安はおおよそ10年とされ、軽量で既存の防水層に大きな負担をかけないため、建物の構造を問わず改修工事に適しています。建物の寿命を延ばし、安心して使い続けたい方は、ウレタン防水材メーカーや専門業者に相談してみてください。
ウレタン防水を用いる際はプライマー選びが重要
アスファルト防水は長年、屋上やバルコニーなどの防水工法として多く採用されてきました。しかし、経年劣化によって表面にひび割れや膨れが生じると、改修工事が必要になります。アスファルト防水からウレタン防水への改修の際には、プライマー選びが大きなポイントです。プライマーとは
プライマーとは、下地と防水材を密着させるための接着剤の役割を担う材料であり、既存のアスファルトと新しく塗布するウレタン防水材を確実に接着させるために欠かせません。プライマーには非常に多くの種類があり、その数は百種類におよぶとされます。また、既存の下地の状態やアスファルト防水の仕上げ方法、さらには劣化の程度によって最適なプライマーは変わります。もし適切なプライマーを使用しなければ、せっかくのウレタン防水層がうまく接着せず、短期間で浮きや剥離が発生してしまう恐れがあるので注意が必要です。
ウレタン防水が適切でないケースもある
しかしどんな状況でも、プライマーを塗れば改修可能というわけではありません。雨漏りがすでに発生していたり、既存のアスファルト防水層に大きな剥がれや膨れが見られたりする場合には、ウレタン防水による改修は適切でないことがあります。下地そのものが不安定であれば、どんなに高性能なプライマーを使っても十分な密着性を確保するのはむずかしいでしょう。そうした場合は、既存防水層の撤去や別の改修工法を検討する必要があります。
アスファルト工事における3つの工法
建物を雨や湿気から守るために欠かせない防水工事の中でも、アスファルト防水は多くの建物に採用されてきました。アスファルト防水には大きく分けて三つの工法があり、それぞれに特徴やメリット、注意点があります。ここでは「熱工法」「常温粘着工法(冷工法)」「トーチ工法」について解説します。熱工法
熱工法は、アスファルトを200〜270℃にまで熱して溶かし、防水シートを積層する工法です。日本では100年以上前から実績があり、130年以上の歴史があるとされる伝統的な工法です。厚みは6〜10ミリと分厚く、水密性や耐久性にすぐれ、寿命は17年以上とされています。そのため、公共工事や大規模施設で数多く採用されてきました。
しかし、施工中に強い匂いや煙が発生することや、施工後の重量が大きく建物に負担をかけることから、小規模建物には不向きです。また、この工法を扱える熟練の職人が減っていることもあり、近年は新築工事を中心に利用される一方で、改修工事での採用は減少しています。
常温粘着工法(冷工法)
常温粘着工法は、改質アスファルトシートを常温で下地に直接接着していく方法です。熱工法と異なり火や高温のアスファルトを使わないため、施工中に匂いや煙が発生せず、室外機や設備がある環境でも安全に作業できます。さらに、シートは1〜2層で十分な防水効果を発揮するため、工期を短縮できるのも利点です。
ただし、剥離紙をはがして貼り付ける方式のため、熱工法に比べて密着度がやや劣るとされ、5〜8年ごとにトップコートの塗り替えなどのメンテナンスが必要になります。それでも安全性や施工性の高さから、改修工事では多く採用されている工法です。
トーチ工法
トーチ工法は、改質アスファルトシートをトーチバーナーで800〜1000℃に炙り、熱で下地に密着させる方法です。防水性と接着性にすぐれており、既存のアスファルト防水層の上に直接施工できるため、マンションや大型建物の改修で多く実績があります。ただし、高温の火を扱うため下地を傷めるリスクがあり、施工場所によっては煙や臭いがこもりやすい点に注意が必要です。また、火を使うために室外機や可燃物が周囲にある場合は適さないこともあります。冷工法と同様、5〜8年ごとのトップコート更新が求められます。