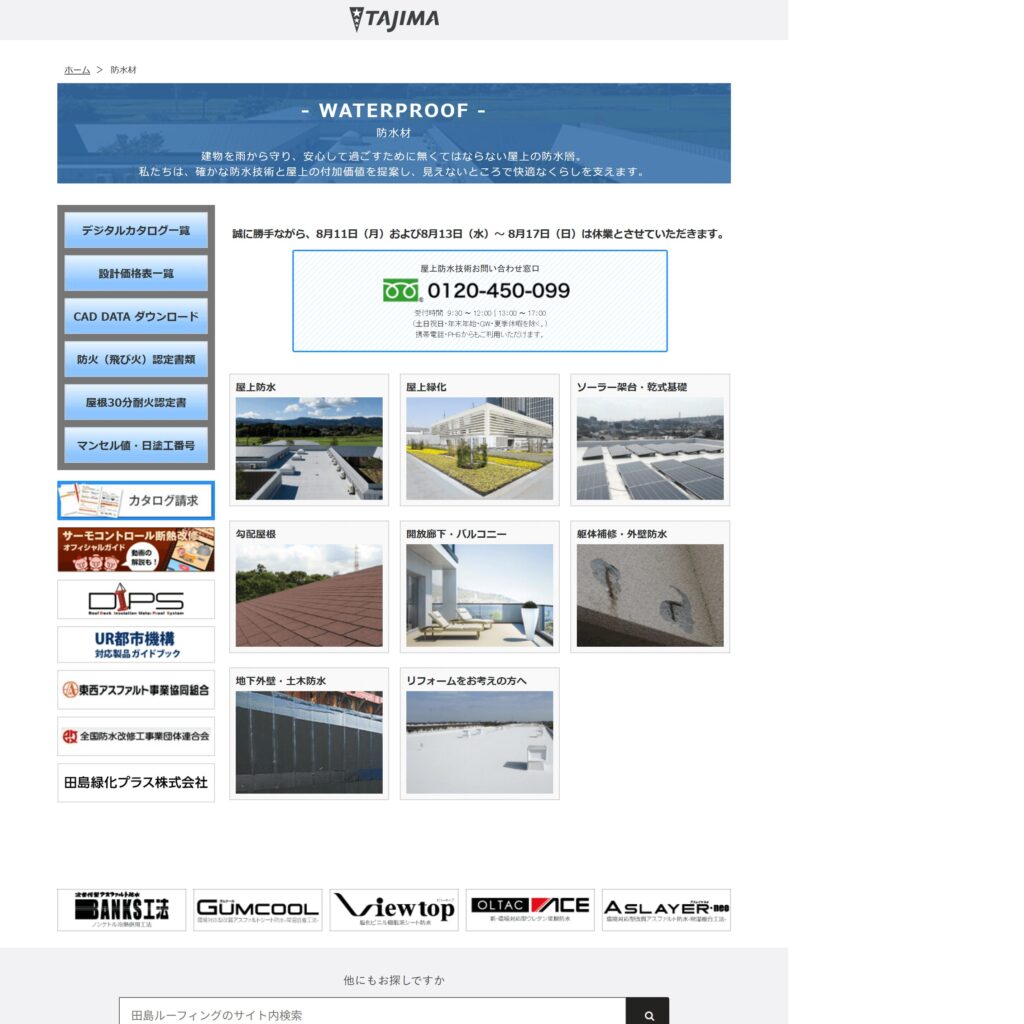防水工事にはさまざまな種類があるため、どの工法を選ぶべきなのか悩む人も多いのではないでしょうか。防水工事は費用が高額なため、工法ごとの特徴や耐久性などを考慮しながら慎重に選ばなくてはいけません。この記事では、代表的な防水工事の工法や選定ポイントを詳しく紹介しますので、参考にしてください。
防水工事の工法主要
防水工事にはさまざまな工法があり、それぞれ施工方法や耐久性、費用が異なります。選び方を間違えると、十分な防水効果が得られない可能性があるので注意が必要です。防水工事の工法主要4種類の特徴を詳しく見ていきましょう。ウレタン防水
ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を何層にも塗布して、継ぎ目のない防水層を作る工事です。どのような形状や場所にも施工でき、建物への負担が少なく費用も抑えられるのが特徴です。施工が簡単で効率的なため住宅をはじめ多くの建物で採用され、依頼側と施工側の双方にとってメリットが大きい工法として人気があります。
シート防水
シート防水は、塩化ビニルやゴム製の防水シートを接着剤や専用機械で下地に固定して防水層を作る工法です。シートの素材は2種類あり、ゴムシートは伸縮性と耐候性に優れ、塩ビシートは耐候性や紫外線、熱、オゾンに強く長持ちします。現在は耐久性の高さから塩ビシートが主に使われ、平面の屋上やベランダなどにも施工しやすく、住宅や商業施設でも幅広く採用されています。
アスファルト防水
アスファルト防水は、アスファルトシートを用いて防水層を作る工法で、防水工事の中でも歴史が古く、実績が豊富で信頼性が高いのが特徴です。重さがあるため建物への負担が大きく、一般住宅ではあまり採用されません。耐久性が求められるビルやマンションの屋上など、大規模な建物で主に施工される防水工事です。
FRP防水
FRP防水は、ガラス繊維シートの上にポリエステル樹脂を塗布して硬化させる塗膜防水の一種です。軽量で強靭なFRPの特性を活かしており、防水層は耐久性が高く人や車の通行にも耐えられます。さらに防水性能が優れている一方で、建物への負担は少なく、住宅や商業施設など幅広い建物で利用される工事方法です。
工法別の耐用年数と費用
防水工事を選ぶ際には、工法ごとの耐用年数や費用を把握しておくことが大切です。ここからは、代表的な4種類の防水工法について、耐用年数と費用の目安を紹介します。ウレタン防水
ウレタン防水は通気緩衝工法で13~15年、費用は㎡あたり6,500~7,500円程度です。密着工法では耐用年数が約10年、費用は5,000~6,000円程度になります。シート防水
塩ビシート防水は機械固定法で耐用年数15~18年、費用は6,500~7,500円程度です。密着工法の場合は耐用年数12~15年、費用は6,000~7,000円程度です。加硫ゴムシート防水は耐用年数10~12年、費用は5,500~6,000円程度となります。アスファルト防水
改質アスファルトシート防水は耐用年数12~18年で、費用は5,000~7,500円程度です。FRP防水
FRP防水は耐用年数10〜15年で、費用は6,000〜8,500円程度です。工法別のメリット・デメリット
建物を長く守るためには、防水工事の種類ごとの特徴を理解することが大切です。代表的な4種類の工法について、それぞれのメリットとデメリットを紹介します。ウレタン防水
メリットは、液状の樹脂を使うため複雑な形状にも対応でき、継ぎ目のない仕上がりになる点です。通気緩衝工法では膨れを防ぎ、耐久性も確保できます。密着工法は工期が短く、コストを抑えやすいことも魅力でしょう。デメリットは、職人の技術により仕上がりに差が出やすく、定期的にトップコートの塗り替えが必要になる点です。通気緩衝工法は特に工期が長く、費用も高めになります。
シート防水
メリットは、下地を選ばず施工でき、耐久性に優れ、メンテナンス性も高いことです。機械的固定法なら工期短縮も可能で、天候の影響も受けにくいです。一方で、複雑な形状に対応しにくく、工事中に騒音が発生する可能性がある点がデメリットとして挙げられます。さらに、ゴムシートに比べると価格が高く、使える場所が限られる場合があります。
アスファルト防水
メリットは防水性と接着力の高さにあり、マンションや大規模建物などで多く採用されています。トーチ工法では既存防水層に重ねて施工でき、冷工法は火を使わず安全で臭いも少ないのが特長です。デメリットは、トーチ工法では高温による下地への影響や煙の発生が問題となります。冷工法は密着性がやや劣るため、定期的なメンテナンスが必要でしょう。
FRP防水
メリットは、ガラス繊維と樹脂を組み合わせた強靭な層が高い防水性を発揮し、短期間で施工できる点です。軽量ながら耐久性に優れ、バルコニーなど歩行部分にも適しています。デメリットは、対応できる業者が少なく費用も高めになりやすい点です。また施工場所に制限があり、どの現場でも採用できるわけではありません。